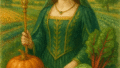スイスチャード(別名:フダンソウ)は「地中海沿岸原産」とされますが、実際にどの国が発祥かまでは明確に特定されていません。
理由としては、
- 古代から地中海一帯(南ヨーロッパ、北アフリカ、西アジア)で自生していた野生ビート(Beta vulgaris)が、各地で食用・栽培化されてきたため。
- 現存する学術文献や植物考古学の証拠では、古代ギリシャやローマの時代にはすでに複数地域で利用されていたことが確認されており、単一の国を「発祥」とは言えない。
ただし、植物分類学的には、
- **東地中海沿岸(現在のギリシャ、イタリア南部、トルコ西岸あたり)**が、スイスチャードに近い原種の生育地と考えられています。
- 古代ローマ人は「Beta」と呼んでいて、特にイタリア半島とギリシャで栽培が広まりました。
結論として、
「発祥国」を一つに絞るのは難しいですが、起源は古代ギリシャ〜イタリア周辺の東地中海沿岸と考えるのが最も有力です。
古代ギリシャやローマでのスイスチャード(フダンソウ)利用について、記録や料理例をまとめます。
📜 古代ギリシャでの利用
- 名称:ギリシャ語では「σίκυον ῥοῦβιον(sikyōn rhoubion)」や、単に「ビート(Beta属の総称)」として記録。
- 栽培:紀元前5世紀頃には、地中海沿岸の畑や庭園で栽培されていました。
- 利用法:
- 葉を茹でて、オリーブオイルと酢(またはワインビネガー)で和える。
- ハーブ(ディルやコリアンダー)と一緒に煮込み、パンや粥と合わせる。
- 医療用途:ヒポクラテスやディオスコリデスの薬草書には、便通を整える・血液をきれいにする作用があると記載。
🏛 古代ローマでの利用
- 名称:ラテン語で「Beta」または「Beta vulgaris」。
紀元前1世紀の作家コルメラ(Columella)やプルニウス(Pliny the Elder)の農書に記録あり。 - 栽培の広がり:
- イタリア半島だけでなく、ガリア(現フランス)やヒスパニア(現スペイン)にも広まった。
- 料理法:
- Moretum(モレトゥム):刻んだ葉をチーズ・ニンニク・ハーブ・オリーブオイルで和えたペースト。パンに塗って食べる。
- オリーブオイル煮:茹でた葉をオリーブオイルとワインビネガーで煮る。
- プルス(Puls):小麦やスペルト小麦の粥に刻んだ葉を加えて煮込む、日常食。
- 医療用途:
- 食欲増進、便秘予防、傷の湿布などにも使われた。
- プルニウスは「葉は血液を清め、根は体を温める」と記述。
🍽 当時のシンプルなレシピ(再現可能)
古代風スイスチャードのオリーブオイル和え
- 葉をよく洗い、粗く刻む。
- 塩を入れた湯で1〜2分さっと茹でる。
- 水を切って皿に盛り、オリーブオイルと少量のワインビネガーをかける。
- お好みでディルやコリアンダーを散らす。
※これは紀元前〜紀元後の地中海で日常的に食べられていたシンプルな方法です。
では、古代ローマの雰囲気を残しながら、日本のキッチンで再現できる
**「現代向け 古代ローマ風スイスチャードの温サラダ」**レシピをご紹介します。
🥗 材料(2人分)
- スイスチャード(茎と葉)… 200g
- エキストラバージンオリーブオイル… 大さじ2
- 白ワインビネガー(または米酢+白ワイン小さじ1)… 大さじ1
- ディル(乾燥または生)… 小さじ1
- コリアンダー(粉または生葉)… 小さじ1/2
- 塩… 小さじ1/4
- 粗挽き黒こしょう… 適量
🍳 作り方
- 下ごしらえ
- スイスチャードを流水でよく洗い、茎と葉を分ける。
- 茎は5cm程度、葉はざく切りにする。
- 茹でる
- 鍋に湯を沸かし、塩少々(分量外)を加える。
- 先に茎を1分半茹で、その後葉を加えてさらに1分茹でる。
- ざるにあけ、水気をしっかり切る。
- 仕上げ
- ボウルにオリーブオイル、白ワインビネガー、ディル、コリアンダー、塩を入れてよく混ぜる。
- 茹でたスイスチャードを加えてやさしく和える。
- 盛り付け
- 器に盛り、仕上げに粗挽き黒こしょうをふる。
- 温かいうちに召し上がれ。
🍷 食べ方の提案
- バゲットやフォカッチャと一緒に食べると、古代ローマ風の雰囲気UP。
- ゆで卵やチーズ(フェタやリコッタ)を添えても相性◎。
🕰 古代風アレンジのポイント
- 調味料は塩・オリーブオイル・ビネガー・ハーブだけにしてシンプルに。
- 可能なら地中海原産のハーブ(ディル、オレガノ、コリアンダー)を使用。
- 酢は白ワインビネガーにすると、古代ローマで使われていた酸味に近づきます。
このレシピは古代ローマ人が日常的に食べていた「Beta(ビート類)の温サラダ」を、
現代でも作りやすくしたものです。