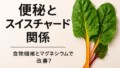ベタレイン(betalains)は、ビーツやドラゴンフルーツ、アマランサス、そしてカラフルなスイスチャードなどに含まれる“天然の色素”です。見た目の色をつくるだけでなく、抗酸化を中心にさまざまな働きが研究されています。
ベタレインの基礎
- どんな色素?
窒素(N)を含む水溶性の色素で、ベタラミン酸という共通の“芯”に、別の分子がくっついて2系統に分かれます。- ベタシアニン(Betacyanins):赤〜紫(代表例:ベタニン/ビーツの主色素)
- ベタキサンチン(Betaxanthins):黄〜橙(代表例:ブルガサンチン、インディカサンチン など)
- どの植物に多い?
主に**ナデシコ目(Caryophyllales)**に属する植物に見られます。例:ビーツ、スイスチャード、アマランス、サボテン(ウチワサボテンの果実)、ドラゴンフルーツなど。
※同じ“赤系色素”でも、アントシアニンとは別物で、一般に同一植物内で両方は共存しません。
体内での働き(研究の現状)
- 抗酸化作用:活性酸素の消去や、脂質の酸化抑制に関する試験管内・動物・小規模ヒト研究が複数あります。
- 抗炎症の可能性:細胞レベルで炎症性シグナルを抑える示唆。
- 代謝関連の示唆:酸化ストレス低減に伴う血管・代謝マーカーの改善が報告された研究もあります。
→ ただし、がん予防や疾病リスク低下を断定できる段階ではありません。食品から“カラフルな野菜果物をバランスよく”が基本です。
吸収・代謝の豆知識
- 水溶性なので消化吸収は比較的速く、一部はそのまま尿に出ます(ビーツ後の“ビート尿”の赤色はベタニン由来)。
- 種類によって吸収率は差があり、インディカサンチンは比較的吸収されやすいと報告があります。
- 体内で分解されつつ、短時間で代謝・排泄される傾向です。
調理・保存でのコツ(色と機能を保つ)
- 熱・光・酸素に弱い:長時間の高温加熱や強い光で分解しやすい。
- pHはやや酸性が安定:レモン汁や酢を少し加えると色持ちが良くなります。
- おすすめ調理:
- 短時間の蒸し・軽いソテー・電子レンジ加熱
- 茹でる場合は短時間&少なめの湯(色素の流出を抑える)
- サラダやマリネなど生・浅漬けも◎(衛生に注意)
- 保存:低温・遮光。切り口はラップ密着で酸化を抑える。
スイスチャードとベタレイン
- スイスチャード(フダンソウ、Beta vulgaris subsp. cicla)は、茎や葉脈の赤・ピンク・黄・橙がまさにベタレインの色。
- 赤〜紫は主にベタニン(ベタシアニン)、黄〜橙はベタキサンチン由来。
- 取り入れ方の例:
- 茎は細切りでレモン+塩の即席マリネ(色・シャキ感キープ)
- 葉はさっとソテーして最後に酢やレモンをひとたらし
- ヨーグルトやフムスに刻んだ茎を混ぜると色鮮やか&栄養プラス
安全性と注意点
- ベタレイン自体は食品由来の天然色素で、ビートレッド(食品添加物E162)としても広く使われています。通常の食事量で安全性は高いと評価されています。
- ただしスイスチャードはビタミンKやシュウ酸も多め:
- ワルファリン服用中はビタミンK摂取の一貫性を医師と相談。
- 尿路結石(シュウ酸カルシウム)既往のある方は量や調理法(茹でこぼし)に配慮を。
まとめ(超要点)
- ベタレイン=ビーツやスイスチャードの“赤〜黄の元”で、抗酸化が期待される水溶性色素。
- 赤系=ベタシアニン、黄系=ベタキサンチン。
- 酸性寄り&短時間加熱で色と成分をキープ。
- 健康効果は前向きなデータが増えていますが、決定打はまだ研究中。彩り豊かな食生活の一員として取り入れるのがおすすめです。