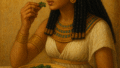静かなる芽生え
パラティヌスの丘に、まだ夏の朝の冷たさが残っていた。女王リウィアは、薄青い石畳をかすめる風の匂いで、その日もテヴェレ川が湿り気を運んでくることを知った。侍女が差し出す薄手のショールを肩に掛け、彼女は自らの薬草園へ向かう。宮廷の華やぎから半歩退いたその一角では、医師たちが摘み取った葉を臼で摺り、香油や酢と混ぜ合わせては、兵士や病人用の軟膏や煎じ薬を拵えている。
その年、ラティウム一帯では春先の長雨のあとに暑気が早く訪れ、畑が息を切らしていた。小麦はなんとか育ったが、葉物は次々と萎れ、市場は緑の少なさに色を失っている。フォルム近くの施粥所には、熱に浮かされた子どもや働き手が列をなし、医師は胆汁の乱れと腸の疲れを嘆いた。油と塩とパンだけでは、人は持たない――それは、リウィアが幼い頃に田舎の別荘で農奴の女たちから繰り返し聞いた言葉でもあった。
薬草園の片隅で、ひときわ濃い緑を湛えた畝が目に入る。白い葉柄を立て、幅の広い葉をたっぷりと広げるその植物は、他の菜が陽に焼かれて伏している中でも、屈せず水気を抱え込んでいる。園丁が刃を入れては、同じ株からまた柔らかな葉が立ち上がるのを待つ。リウィアはしゃがみ込み、葉の裏を指でなぞると、うっすらと塩の香りを含んだ青い匂いがした。
「この葉は?」
「フダンソウでございます、奥方。いま人々はスイスチャードとも申すとか。茹でて油と混ぜれば腹にやさしく、塩気にもよく合います。乾きにも強く、同じ畝から何度も刈り取れましょう」と園丁は答える。
「何度も?」
「ええ。一月のあいだに三度ほど。茎を深く切りすぎなければ、すぐに新しい葉が上がります」
彼女は台所へと足を向け、さっと湯がかれたその葉を小皿で口にした。舌に残る苦みは浅く、油に抱かれた甘みが後からゆっくりと滑ってくる。塩と酢、少しの発酵魚醤を落とせば、疲れた身体でも拒まない味だ。リウィアは匙を置くと、侍従を呼び、周辺の別荘の管事(ヴィリクス)たちを午後の会合に招くよう命じた。
昼前、彼女は密やかに市の南、アヴェンティヌスの丘下にある施粥所を訪ねた。扉口には秋すでに来ぬといわんばかりの熱気がこもり、薄い麦粥に刻んだ草を落として配る女たちの手元は、わずかに震えている。列の子どもの頬は青白く、兵士上がりの男は腹を押さえ、咳に身を折った。彼女はひざまずき、粥の表面を覗き込む。そこにはほとんど葉らしい葉はなく、油の虹が薄く揺れているだけだった。
「葉が足りぬのです」と施粥所の女は言った。「畑のものが苦しんでいます。キャベツもレタスも背を伸ばすばかりに固くなり、柔らかなものが出ないのです」
「柔らかなもの――胃に負担の少ないものが要るのですね」
「熱の出た者にも、歯の弱った老人にも」
夕刻、パラティヌスの広間に管事たちが集い、リウィアは石板に描いた簡単な畑の図を示した。彼女は飾らない口調で、見たばかりの施粥所の様子を語り、薬草園の一角で見たフダンソウの強さを説明する。
「わたくしたちは穀物の安定に心を砕いています。けれど、健康はパンだけでは立ちません。油に合い、消化を助け、水を多く欲しない葉――そういう野菜が、暑さのなかで人々をつなぎとめます」
管事のひとりが遠慮がちに口を開く。「奥方、確かにあの葉はよく育ちますが、見た目が地味で、市に持っていっても値がつきませぬ」
リウィアは笑んだ。「市に並べるだけが野菜の務めではありません。家の鍋に入ってはじめて、その力を発揮するものもあるのです。刈り取ってはまた伸びるなら、家ごと、街区ごとに畝をつくればよい。女や子どもでも世話ができます」
彼女はさらに、各地の別荘や都市の中庭(ホルトゥス)に小さな畝を起こし、種を分け、刈りどきを揃えるだけの簡単な手引きがあれば、数週間で施粥所に緑を戻せる計算を示した。必要な水は朝夕の潅水で足り、土は肥えすぎていないほうがよい――園丁から聞いた素朴な心得を、紙片に書き付けた。
会合が散じ、人影の薄くなった広間で、リウィアは窓辺に立った。丘の向こうに赤く沈む日の光が、テヴェレ川面に細い道を引いている。彼女は、若き日、娘を病で失いかけた夜のことを思い出した。湯気の立つ鍋から立ちのぼる青い香りに、かすかな希望を見いだしたあのときの感覚。食卓が人を救うという直感は、彼女の胸から離れたことがない。
「健康は、国家の沈黙の石垣のようなものです」と彼女は独り言のようにつぶやいた。「崩れ始めてからでは遅い。音のしないうちに、積み直さねばならない」
翌朝、彼女は書記に命じ、簡潔で温かな言葉を綴らせた。市民に向けて、そして各都市の評議会、軍の補給官、施粥所の監督者に向けて。強制でも命令でもない、「すすめ」の文。――鍋に緑を戻そう。家々の片隅に、柔らかな葉を育てよう。パンと油に、もうひと匙のやさしさを添えよう――。
その手紙がいくつもの封蝋に閉じられ、伝令の鞄に収められていくのを見届けながら、リウィアはまだ誰も知らない物語の始まりを確信していた。葉は静かに、人々の体を内側から支える。彼女の視線は、宮廷の壇上ではなく、ローマの台所へ向いていた。物語は、ここから動き出す。
豊穣を運ぶ風
夏が深まるにつれ、リウィアの書簡はローマ各地へと行き渡った。封を解いた者たちは、その端正な文字の奥に、ただの貴婦人ではない確かな意志を感じ取った。そこには威圧的な命令文はひとつもなく、「やってみませんか」という穏やかな提案と、簡潔な栽培法、そして葉を鍋に落とすときの香りや舌触りまでが、生き生きと綴られていた。
最初に応えたのは、アッピア街道沿いの小さな町の評議会だった。干ばつで菜園が壊滅していた彼らにとって、「少ない水で、何度も収穫できる」という植物の性質は、まるで天からの救いのように響いた。町外れの空き地が耕され、土の塊をほぐす手のひらに種が落ちた。老人は日陰から若者に声をかけ、子どもたちは種まきの列をまっすぐに保とうと真剣な顔をしていた。
数週間も経たぬうちに、町のあちこちで濃い緑の葉が陽を弾き返すように広がった。ある老婆は、昼下がりに柔らかく煮た葉を孫に与え、その頬が赤みを取り戻すのを見て涙をぬぐった。兵士上がりの男は、疲れきった仲間に塩と油で和えた葉を分け、「これで足がまた動くぞ」と笑った。
ローマ市内でも、宮殿の外壁沿いの細長い空き地や、中庭(ホルトゥス)の片隅で、小さな畝が生まれ始めた。市場の行商人が、まだ珍しいこの葉を少量束ねて売りに出すと、初めは見向きもしなかった市民も、口にした者から評判が広がっていった。「噛むと甘い」「湯通ししても色が落ちない」「子どもが嫌がらない」――噂は、パン職人の耳にも、魚屋の耳にも届いた。
リウィアは時折、身分を隠して施粥所や市場を歩いた。籠いっぱいのスイスチャードを持ち込む農家の姿を目にすると、心の中で静かに頷いた。彼女は決して「自分の功績」として語らず、むしろ「これは昔からある庶民の知恵を、もう一度思い出しただけ」と答えた。
その頃、ローマの軍営からも報せが届いた。遠征先で疲弊した兵士に、この葉を使った温かいスープを供したところ、下痢や熱の症状が減ったという。軍医はその報告を詳しく書き、補給官に送った。補給官は、それをリウィアのもとに届け、「この葉は剣よりも兵を守ります」と短い言葉を添えていた。
秋の初め、パラティヌスの丘の薬草園は、リウィアが各地から持ち帰らせた種でさらに多様になっていた。赤い茎、黄金色の茎、そして深い緑一色のもの――どれもが瑞々しく立ち上がり、彼女の指先に未来の手応えを伝えてきた。
だが、喜びとともに、ひとつの影も忍び寄っていた。市場では、急増したスイスチャードの取引を快く思わぬ商人が現れ、他の野菜の売れ行きへの影響を口にし始めたのだ。「緑が安く手に入りすぎれば、キャベツもレタスも値が下がる。農家は困る」――その声は、やがて評議会の一部にも届き、慎重論として形を取り始めていた。
リウィアはそれを知ると、夜更けに執務机に向かった。蝋燭の灯が揺れる中、彼女は書簡の束を前に、どうすればこの新たな緑が、争いではなく共存の道を歩めるのかを考え続けた。外では、夏の終わりを告げる涼しい風が、静かに宮殿の石壁を撫でていた――。
揺れる葉、揺れる心
初秋のローマは、朝夕こそ涼しさを帯びたが、日中はまだ夏の熱が石畳に残っていた。市場の喧噪は活気を増していたが、その裏で、小さな波紋が広がりつつあった。スイスチャードが市井に定着し始めると、今まで葉物野菜を支えてきた商人や農家の一部が眉をひそめた。
「このままでは値崩れだ」
「レタスやキャベツが売れなくなる」
「女王が薦めたからといって、我々の畑を無にされては困る」
彼らの声は、市場の路地から評議会の会議室まで、ゆっくりとしかし確実に届いていった。反対派は「女王の慈愛」という美名の陰に、国家経済の歪みを生みかねない種が潜んでいると訴えた。
その頃、リウィアのもとにも風向きの変化が届いた。パラティヌスの執務室で、彼女は報告書を手に取る。そこには、地方の商人組合から送られた正式な嘆願書があった。言葉は丁寧だったが、内容は鋭く、スイスチャードの急速な普及を一時的に抑えるべきだと記されていた。
夜、広間に集まった側近や園丁、軍の補給官たちは、静かにリウィアを見守っていた。
「奥方、これは容易なことではありません」と補給官が切り出す。「葉は人々を救っています。しかし、市場の均衡を崩せば、別の場所で飢えや不満が生まれます」
「しかし放っておけば、施粥所や遠征地の兵たちはどうなる?」と軍医が反論する。
会議の空気は張りつめた。リウィアは椅子から立ち上がり、深く息を吸った。
「葉はただの食べ物ではありません。健康を守る盾です。しかし、盾が刃になってはならない。人々の間に争いを生むなら、私たちは方法を改めねばなりません」
翌日、彼女は一計を案じた。スイスチャードの普及を「代替」ではなく「補完」として位置づけるのだ。畑の一部をこの葉に割き、季節や用途に応じて他の作物と組み合わせる栽培法を広める。さらに、商人や農家には、スイスチャードを使った保存食や加工品――干し葉、酢漬け、塩漬け――の新しい販売路を提案した。
しかし、それを受け入れる者ばかりではなかった。ある商人は「新しいやり方など試す気はない」と席を立ち、別の農家は「加工品など富裕層しか買わない」と顔をしかめた。反発は根深く、説得は容易ではなかった。
その頃、偶然にもローマ近郊で小さな疫病が発生した。発熱と倦怠感を伴い、体力の低い者から倒れていく病だった。医師たちは施粥所に駆け込み、消化の良い食べ物を求めたが、青物の備蓄はほとんど残っていなかった。
リウィアはその知らせを聞くや否や、すぐに指示を出した。
「各家庭と施粥所にスイスチャードを回せ。市場価格はこの際問わない。命が先だ」
数日後、病の広がりは徐々に収まり、人々の間で「女王の葉」という呼び名が自然と口にされるようになった。反対派の中にも、この出来事をきっかけに態度を軟化させる者が現れた。
しかし、完全な和解にはまだ遠い。リウィアは知っていた――葉が人々の体を救ったとしても、人の心を救うには、さらに時間と知恵が要るということを。
秋風が薬草園を吹き抜け、黄金色に染まり始めた葉の間で、リウィアは静かに次の一手を考えていた。
「この緑を、争いの種ではなく、平和の印に変える」
その決意は、彼女の中でますます鮮やかに、そして重くなっていった。
緑は国を繋ぐ
初冬のローマは、灰色の雲が低く垂れ込み、街路樹の影も短く縮んでいた。寒さは人々を家の中へと追いやり、施粥所の前には、厚手の外套を着込んだ市民の列が再び伸びていた。だが、かつてのような青物不足の深刻さは、もうなかった。
スイスチャードの畝は、冬の冷気の中でも葉を広げ、深い緑を保っていた。葉の下には、まだ若い芽が次の収穫を待っており、それらは市の倉庫や施粥所の大鍋へ、そして軍営や農家の食卓へと途切れなく運ばれていた。
リウィアは、パラティヌスの広間で再び評議会を開いた。今回は、商人、農家、軍の補給官、市場の仲買人、施粥所の監督者――すべての立場の代表が同じ長い卓を囲んだ。
彼女は立ち上がり、落ち着いた声で語り始めた。
「この葉は、誰かの畑を奪うために育てられたのではありません。誰かの命を守るために育てられたのです。畑も市場も、命を守るための仕組みでなければなりません」
そして、彼女は新たな制度を提案した。
- 季節ごとの栽培配分:春夏は葉物の多様化を保ち、秋冬はスイスチャードを中心に補完する。
- 加工・保存の普及:余剰分は干し葉、酢漬け、塩漬けにし、市場や軍備蓄として活用する。
- 利益の分配:施粥所や公共事業への供給分に応じて、農家や商人へ補助金を支給する。
最初は静まり返っていた会議の場に、やがて小さな頷きがいくつも見え始めた。商人たちは、保存加工による新たな販路に興味を示し、農家たちは収穫時期の安定に安心を覚えた。補給官は、遠征時の兵糧計画にこの葉が不可欠だと力説した。
冬至を過ぎた頃、ローマの市場には、赤や黄金の茎を持つスイスチャードが彩りを添えていた。酢漬けの瓶が並び、干し葉を売る屋台には兵士や旅人が列を作った。施粥所の大鍋からは、湯気とともに青い香りが漂い、子どもたちが嬉しそうにパンを浸して食べていた。
ある日、リウィアは身分を隠して市場を歩いた。老婆が孫に言っている声が耳に届く。
「この葉はね、女王様がすすめてくださったんだよ。みんなの命を守るために」
孫は驚いた顔で葉を見つめ、その緑を両手で大事そうに抱えた。
パラティヌスの丘に戻ったリウィアは、薬草園の畝の間をゆっくり歩いた。冬の陽は低く、葉の上に淡い金色を落としている。
彼女は立ち止まり、かつて自らが口にした言葉を思い出した――
「健康は、国家の沈黙の石垣のようなもの」
今、その石垣は、静かに、しかし確かに積み直されたのだ。
風が葉を揺らし、緑がさざ波のように広がっていく。ローマの街もまた、その緑の下でひとつに繋がっていた。